新潟県は全国都道府県の中で5番目の広さを有し、弓なりに長く延びる越後と、日本海上の佐渡ケ島とに分かれています。歴史的にも関西、関東、東北の文化交流の接点に位置していますので、全体像を端的に表現することは難しく、新潟県の特色は、むしろこのような多様な風土の中で、多彩な文化を育んで来たところにあると言えるでしょう。現に県内各神社の祭礼なども大変バラエティに富んでいます。
本県の4700社余りに及ぶ神社数が全国一だということで話題にのぼることがありますが、これには、明治の頃、新潟県は全国で最も人口が多かったこと、或いは明治末期に時の政府が進めた神社合祀政策の影響を比較的受けなかったことなどが背景にあると考えられます。人口が多かったということは、かつて日本人の9割が農業によって生活を成り立たせていた時代に、広い穀倉地帯を有し、収穫高が大きかったことが関係しています。人口の多さが自然村(農耕・漁労を通じて、自然に形成された村落共同体)の多さにつながり、必然的に神社数も多かったのだということになります。その意味では、新潟県は神社の自然な成り立ちを今に伝えていると言えるでしょう。
延長5年(927)に完成した『延喜式』神名帳に官社として登載されている神社を式内社と呼び、越後、佐渡では63社を数えます。優に千年以上の歴史を有する、これら式内社のほとんどは、今も現に鎮座しています。幾星霜を経て信仰の道筋が途切れなかったということは、当然のことながら、それぞれの神社の氏子・崇敬者の方々の篤い崇敬心の賜です。
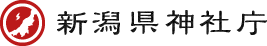
 コラム
コラム


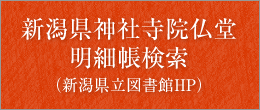 新潟県神社寺院仏堂明細帳検索
新潟県神社寺院仏堂明細帳検索